

動画ソフトVideoProcレビュー。メリット・デメリット・無料でできる範囲

データ復旧ソフトEaseUS Data Recovery Wizardのレビュー【ゴミ箱削除復元ソフト】

釜山の電源wifiノマドカフェ!@西面・南浦洞

釜山ひとりごはん!1000円以内・クレカOK!南浦洞/西面/海雲台/チャガルチ

プーケットからピピ島へ安い行き方!現地ツアーで6000円!パトンビーチからスピードボート
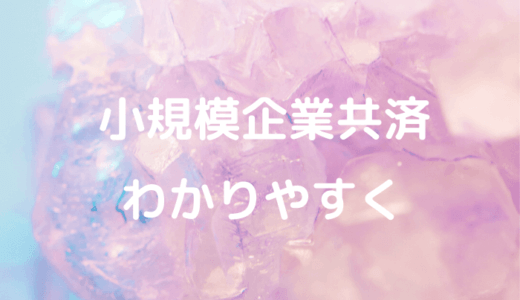
小規模企業共済をわかりやすく!申し込みの流れ・12月加入方法・経営セーフティ共済との違い
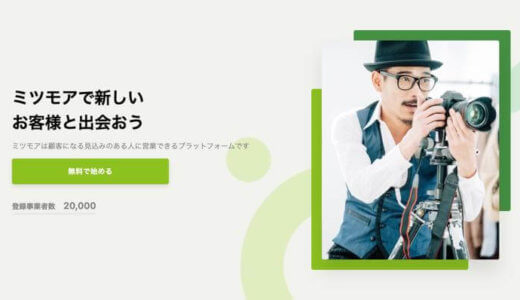
クラウドソーシング・営業代行でもない営業方法ミツモア

タイで猫に噛まれてワクチン5回分6万円かかったけど無料にできた話
